for
future
architect
for
future
architect
建築教育のあり方を問う。
学生の自主性に任せるだけの教育になっていないか?単位を取らせることが目的になっていないか?教授が研究室にこもり閉鎖的になっていないか?画一的ではなく、一人一人の個性を伸ばす教育になっているか?デザインに偏重したバランスの悪い建築になっていないか?建築家としての立ち場から教えられることはもうないか?何より授業がワクワクするようなものになっているか?
社会に役立つ技術者を育てることを使命とし、これまでの建築教育のあり方を一つひとつ見直してきました。
建築を本気で学びたい若者を待っています。
feature
特徴
01社会に役立つ技術者を
育成するという伝統
本学は、大阪の街を作る時に不足する技術者を育てようと、夜学から始まった大学です。伝統的に即戦力の専門技術者を育てる風土があり、本学科の卒業生は社会での評価が高く、それがほぼ100%という高い就職率に反映されています。教授と生徒との距離が近く、相談に乗りやすいように研究室の扉はいつも開かれています。外部の設計コンペにも積極的に参加を促し、建築新人戦2014では、本学科の鈴江佑弥君(建築4年)が「最優秀新人賞」を受賞しました。これは、学科教育のひとつの成果です。


02建築学の幅広い分野を
バランスよく学習
人文科学や社会科学、自然科学などの広範囲な学問分野と融合した学問的性質を持ち、学ぶほどにその可能性を広がりを感じるのが、建築学の魅力です。高度な専門教育に加えて、幅広い教養や芸術への理解を深める授業も展開。<計画・設計><建築環境><構造><材料>の4つの分野を総合的に学習します。設計演習の授業では、必ず構造タイプを指定し、現代建築に必要な強(構造)・用(機能性)・美(デザイン)の3つ要素がバランスよく設計ができるように指導します。

03手を動かして考える教育で
スケール感を体得
設計演習の授業では、3年次後期までは、コンピュータではなく手で図面を描くことを推奨しています。また、他校にはない木造課題も出題し、1/100模型や構造模型も提出物として要求し、身体でスケール感を養えるような教育を行います。手描きの図面は「一級建築士試験」においても課される内容であり、こうした教育の成果もあり、大阪工業大学出身の一級建築士合格者数は西日本の大学で常にトップクラスです。
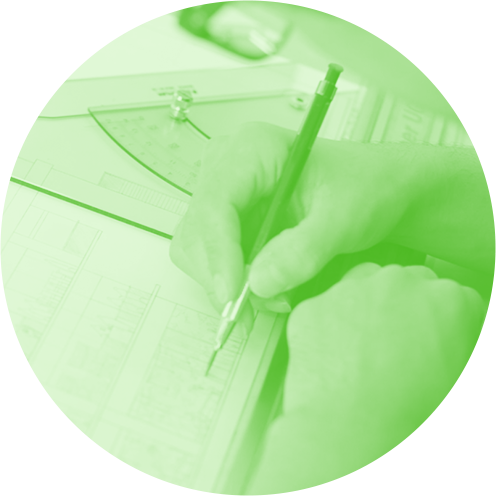

04実際の現場に触れ向上心・
向学心を磨く
実際の建築物を視察したり、西日本でもトップクラスの規模を誇る八幡工学実験場では、構造・耐火実験などを行い、実物に触れて向上心・向学心を養います。また、建築業界の第一線で活躍する先輩方から、実社会のニーズに即した技術や知識を学ぶ機会を設けています。設計演習の授業では、課題の内容を「クライアントからの依頼内容」として、提出期限を「納期」として捉え、スケジュール管理を徹底。実社会で役立つ技術者を育てるため、早いうちから実践的な教育を行っています。






